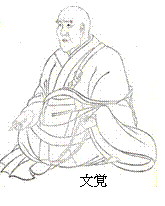 |
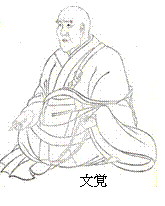 |
武士の歴史 第4回
~鎌倉幕府成立~
| 鎌倉幕府成立 |
武士の置かれた環境 鎌倉幕府成立までは地方豪族の地位は常に不安定でした。また武士と庶民との区別もあいまいでした。日常生活においては農耕に従事し、こと有るときには武器を持ち、家人・郎党などを従え騎馬にて戦いに臨みました。このように平常時には外見上農民と武士の区別はなかなか難しかったのです。 武士たちは自分達の土地を守るために、自ら開拓した土地を荘園や神社に寄進し身分の安定をはかろうとしました。寄進すると言っても事実上は武士本人が支配し、名義借料を払うといった意味です。しかし寄進した貴族や寺社の力が弱まると、力有る者から狙われ安全ではなくなってきますし、寄進した貴族や寺社の力が増大してくるとその権威を笠に着て年貢の増加などを言って来る場合があります。このように地方武士はその支配権を維持するためには、常に周囲の情勢に気を配り、中央政府の権力闘争にも敏感にならなければなりませんでした。 ですから、武士たちは領地を寄進するに当っても一ヶ所の荘園に寄進するのではなく、複数の荘園に分割して寄進し危険の分散をはかりました。これは危険の分散をはかるのと同時に荘園同士を牽制させる意味合いもありました。 こういった不安定な状況から抜け出すためにも武士は自分達の代表を棟梁として担ぎ、確固とした権力の安定を望みました。 |
| 頼朝が担がれた訳 |
| 棟梁と仰ぐ人物は、家柄、血筋が良い人物でなければ誰もが納得しません。同じ土着の有力な武士から選ぶとかえって争いの元となってまとまりがつきませんので、誰もが文句を言うことが出来ない存在、「血筋」つまり皇室出身の有力な武士を中心として結束する道を選びました。その有力な武士の代表が源氏であり平氏であったのです。 前九年、後三年の役の後、関東の武士たちは数々の武功を立てた源義家を棟梁とし、義家の実力、権威でもって所領を安堵してもらおうと結束しました。しかし、義家は平治の乱で敗れ、代わって朝廷の実権を握った平氏に東国の武士たちは支配されるようになりました。当時の東国の武士たちの心境を「源平盛衰記」に「諸国の源氏は国々の百姓となって、国では目代(国司の代官)に従い、荘では、預所(あずかりどころ)に仕えて、公事、雑役にかりたてられ、夜も昼も安き事なし」と書かれているような状態でした。 関東の武士たちは、国司の目代や荘園の預所にこき使われ、不安な日々を送っていたのです。彼等はおりあらば反旗をひるがえす機会をうかがい、彼たちの望みを叶えてくれる棟梁の出現を待ち望んでいました。彼たちの望みとは「本領安堵」です。 石橋山で大敗北を喫した頼朝が、房総半島に逃れた後わずか四十日足らずで立ち直り鎌倉に館を構える事が出来たのを奇跡だと言う人がいますが、当時武士の代表であるはずだった平家が貴族化し、世の武士らはその権威を脅かす事に対する不満がたまっていた為、機は熟しており平家追討には絶好のタイミングだったのです。 そして頼朝が掲げたのは「本領安堵・戦功に応じた新たな所領を恩賞として与える」でした。これこそが関東武士たちの最大の念願でした。その支持を得るために頼朝は房総半島に逃げたときに味方しない国府を襲い、味方した者にその領土を分け与える事で勢力を広げていったのです。 頼朝は三十一歳の時に北条政子と結婚し、やがて北条の村に館を構えました。北条氏にとっては中央の貴族の血が流れ込む事によってその支配力が更新される事となり地方豪族にとっても望ましい事でした。 今の韮山温泉辺りに館を構えた頼朝のもとへ土肥実平や三浦氏、千葉氏の若者など、日増しに出入りする武士たちの数も増えてきました。その中に文覚(もんがく)という僧がいました。文覚は元武士で摂津国(大阪府)に勢力を張っていた渡辺党の一族で遠藤盛遠(もりとう)という者です。盛遠はその昔平清盛と同年代で院の武者所に共に仕える仲間でした。 |
|
僧文覚と袈裟御前(けさごぜん) |
盛遠は博学、剛毅かつ雄弁で朝廷からも学問料を支給され将来を有望視されていました。彼はひたむきで、物事に対して徹底的に追求しなければおさまらない性格でした。恋に関してはなおさらで、理性を失い狂にちかい感情の持ち主でした。 盛遠と同じ武者所に仕えている源渡(わたる)という者がおり、この渡の妻である袈裟御前は絶世の美女でした。盛遠は人妻である袈裟御前に横恋慕し、一途であるがゆえに命がけで袈裟御前に言い寄っていきました。袈裟こそ災難でした。盛遠は言い寄り、彼女に返事を迫りました。思案に暮れた袈裟は盛遠に「主人が生きているうちは、あなたの心に従う事が出来ません。主人に風呂をすすめ、髪の汚れを洗わせ、酒を飲ませて寝かせます。そっと枕に近づき濡れ髪に触れたら一刀のもとに首を打ち落としてください。良人は、打ち物取っては、強者(つわもの)ですから、そっと枕に近づき濡れ髪がお手に触れたら、一太刀(ひとたち)で、首打ち落してしまうことです。」と言い含めました。 盛遠は袈裟御前の言う通りに夜陰に忍び込み見事に源渡の首を討ち取り、縁側に出て討ち取った首を月明かりにかざして見て見ると、恋人である袈裟御前の首であることに驚き遁走(とんそう)し、後に出家して文覚と名乗ったのです。以後、真冬の那智の滝に打たれるなどの荒行を重ね「荒ひじり」と呼ばれるようになり、名を世に高めた人物です。京都、西北にある神護寺の再興のために資金集めをしていた時に、後白河法皇の御所で邪険に扱われたことで悪口雑言を吐いた廉(かど)で伊豆に流されました。 ここで皆さんは、殺人を犯した人間が京都に舞い戻り、捕らえられもせずに堂々と資金集めが出来たのかと不思議に思われると思います。当時は「獄前に死人ありとも、訴えなければ検断(けんだん:犯人の捜索、逮捕など)なし」と云われており、殺人がおこなわれたとしても、訴訟人がなければ刑事事件にならないとの社会通念がありました。ただし、幕府や要人を襲った場合には極めて厳しい追及を受けました。 伊豆に流された文覚は早速頼朝の所へ訪ねて行き平家打倒を懇々と説きます。しかしこの時の頼朝は平家打倒など全く考えておらず、文覚の誘いをかえって迷惑と思っていました。彼は伊豆の土地で血筋の良い地方豪族として一生を終える事を望んでいたのです。平家物語に、文覚が帰った後「あの坊主めが、余計な口出しを・・・」と文覚が陰謀を暴露した後の心の動揺が描かれています。 |
| 源頼朝、平氏打倒に立ち上がる |
| 一一八〇年四月後白河法皇の皇子、以仁王(もちひとおう)と源頼政が平氏打倒の兵を挙げ、頼朝の叔父源行家が山伏の姿に身を変え以仁王の親書(王の令旨りょうじ:皇子が出す文書のこと)を携え各地の源氏のもとを訪れました。四月の末には頼朝の所をたずね親書を手渡していましたが、心に迷いのある頼朝は受け取ってから数ヶ月の間、以仁王、頼政敗北の知らせを聞きながらも動こうとはしませんでした。しかし、彼の思惑とは関係なく諸国の源氏追討が計画され、遂に頼朝は挙兵せざるを得なくなったのです。 頼朝が立ち上がったとき、関東の大豪族の一人、三浦義明が「源氏代々の家人である自分は、いまその貴種、再興の時に巡り会う事が出来て誠に幸せである。義明の生きている間に源氏の家を興したまわんことのうれしさよ。」と言って三浦一族を結集し頼朝の旗揚げに応じました。三浦家にいくら実力があっても、棟梁にはなることは出来ません。つまり天皇の血筋を受けた者でなければ棟梁になることは出来ないのです。 頼朝の旗揚げを支えたのは関東の有力豪族たちである事はすでに話しました。そして富士川の戦いで勝利した頼朝が、敗走する平家軍を追撃し上洛しようとしたのを止めたのも坂東出身の、上総広常、千葉常胤、三浦義澄などの豪族でした。彼等はいずれも坂東平氏の末流です。彼たちの目的はあくまでも坂東に朝廷から干渉されない独立した武士の国を造る事に有ったのです。 政権を樹立し権力を手に入れたにもかかわらず、何かにつけて朝廷に配慮する頼朝に対して彼たちは不満を持っていました。広常は「なんで朝廷のことばかり気にするのか、坂東にあって堂々と構えておればいいのに」と頼朝の事を批判していました。しかし挙兵から二年過ぎた一一八三年に、政権が安定した頼朝は広常に謀反の疑いを掛け梶原影時に命じて、広常が双六(すごろく)に興じている最中に不意を付いて殺害させました。ここに頼朝は坂東独立主義を放棄したのです。 頼朝は後年、後白河法皇と会談したときに「広常は最大の功臣の一人であったが、天皇に対し謀反心をもっている男でしたので、このような者を家臣にしておくわけにはゆかぬと思い、殺してしまいました。」と語ったと言われています。 一一八三年は頼朝の鎌倉政権の支配が関東及び北関東一円に広がり、朝廷より「東海、東山両道の国衙領、荘園の年貢は国司・本所のもとに進上せよ。もしこれに従わぬ者が有れば、頼朝に連絡し命令を実行させよ」といった勅令が宣旨(せんじ)として交付された時期です。 |
| 頼朝全国支配 |
関東地方しか支配していなかった頼朝が全国の支配に乗り出せたのは義経の反旗によってです。義経に頼朝討伐の院宣が出されたのを知った頼朝は一一八五年(文治元年)大軍を整え攻め上る体制ととり、北条時政に一千の兵を従わせ上洛させました。この時義経は西国に逃れようとしたが嵐に遭い失敗し、既に行方をくらましていました。時政は後白河法皇が頼朝追討の院宣を出した事に対して詰め寄り、逆に義経追討の院宣を出させ、義経の行方を探索する名目で「守護、地頭」の地方役人を全国におく事を約束させました。このことは大変歴史上大きな意味を持ちます。 守護・・・各国の警察権をつかさどる職 地頭・・・公領、荘園などの治安維持、管理、年貢の徴収を請け負う役人 今まで続いてきた、京都の王朝国家が武士の力に屈服し、武士に政権を譲った事になります。鎌倉幕府成立は学校では頼朝が征夷大将軍に成った一一九二年と教わった事と思いますが、一一八五年頼朝が朝廷の勢力をしのいだ事からこの年を鎌倉幕府設立と考える学者もいます。 以上 |
瀬戸塾新聞28号掲載 |
| |